タグ:『』の記事一覧
知られざる現実。ひれあし類が減っている理由とは?
国内の水族館や動物園では13種類のアシカやアザラシ、セイウチを見ることができます(2025年11月時点)。しかし中には近い将来その姿を見られなくなる可 […]

ひれあし図鑑の公式グッズができました!
今日はお知らせになります。このたびひれあし類のオリジナルグッズを販売することになりました!SUZURIで販売していて、現時点では4種類の生き物でそれぞ […]

アシカの赤ちゃんはなぜ白くない?
アザラシの赤ちゃんって真っ白で小さくて可愛らしいですよね。たったひと月ほどしか見れない姿ですが、あの可愛さが忘れられず、白いアザラシグッズを持っている […]

八景島シーパラダイス~生後2週間のオタリアの赤ちゃんに出会った~
今回で会えたひれあし類 今回は八景島シーパラダイスを紹介します。9/11に訪問しましたが、日中は残暑とは思えない強い日差しのなか歩き回ったのでかなり辛 […]

ゼニガタアザラシとワモンアザラシの違い
国内の水族館で見れるアザラシの中でもダントツで間違られるのがこの2種類だと思います。どちらも名前の由来になった模様が体中にありますが、同じような形、、 […]
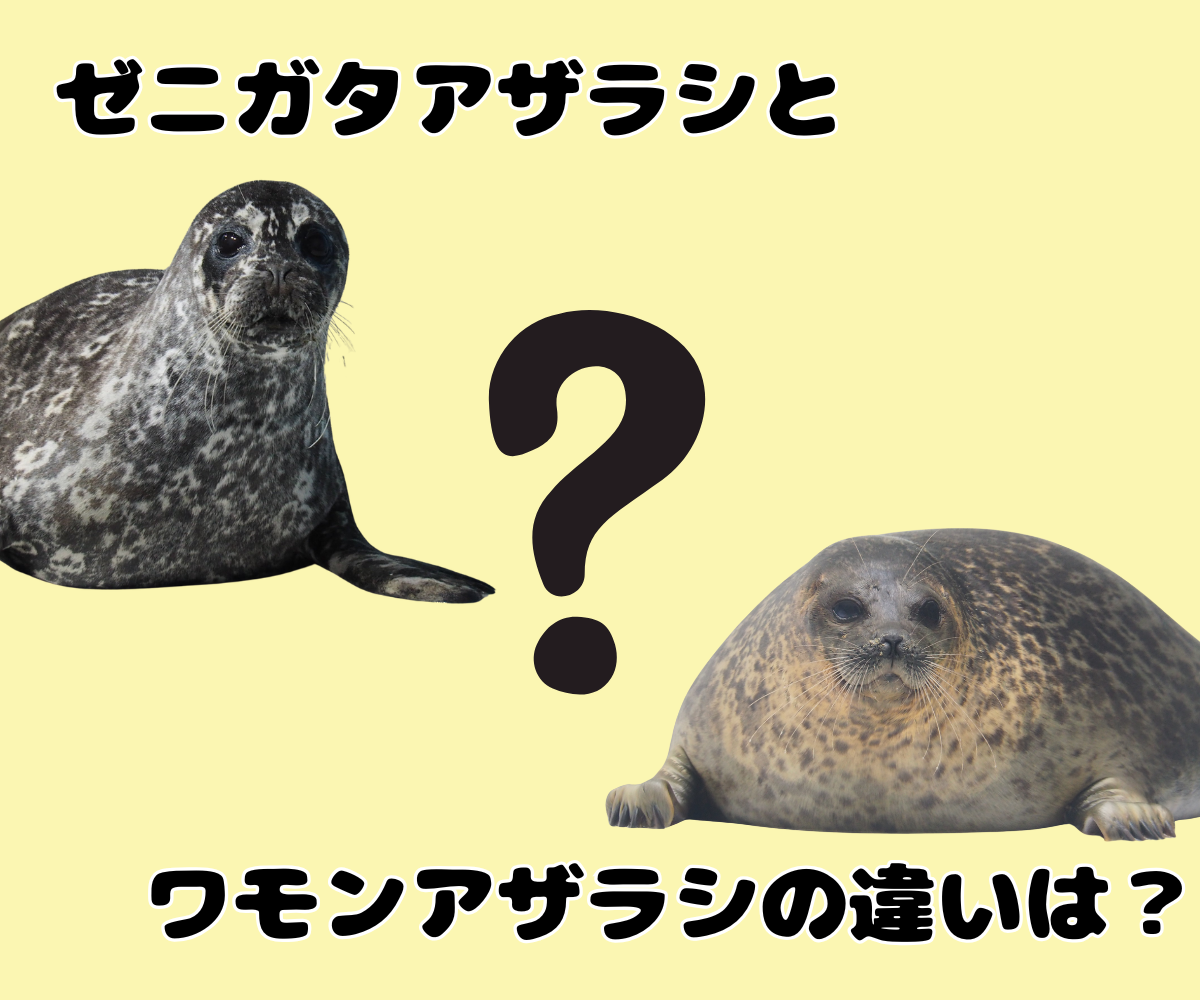
アシカやオットセイが食べるものは?
今回はアシカたちが食べるものについて紹介します。水族館の解説などでも紹介されてますが、なかなかぴんと来ない人もいるのではないでしょうか?今回はそれぞれ […]

ひれあし類はどこで寝る?
哺乳類なのに海で暮らすアシカやアザラシはどこで寝てるのでしょうか?陸?海?そもそも水中で息できるの?普段見れないひれあし類の睡眠方法について紹介します […]

京都水族館~圧倒的水中感のオットセイ水槽へ~
今回は京都水族館を紹介します。京都駅から車で10分とアクセスがいい場所でした。ただ京都の駐車場は水族館も含め基本有料(しかも有名なお寺の近くだと高い、 […]

トドとオタリアとアシカは一緒?紛らわしいひれあし類の名前を解説!
水族館や動物園で見ることができるアシカやアザラシなどのひれあし類。解説パネルを見ると「カリフォルニアアシカ」や「トド」「オタリア」など種の名前が書いて […]
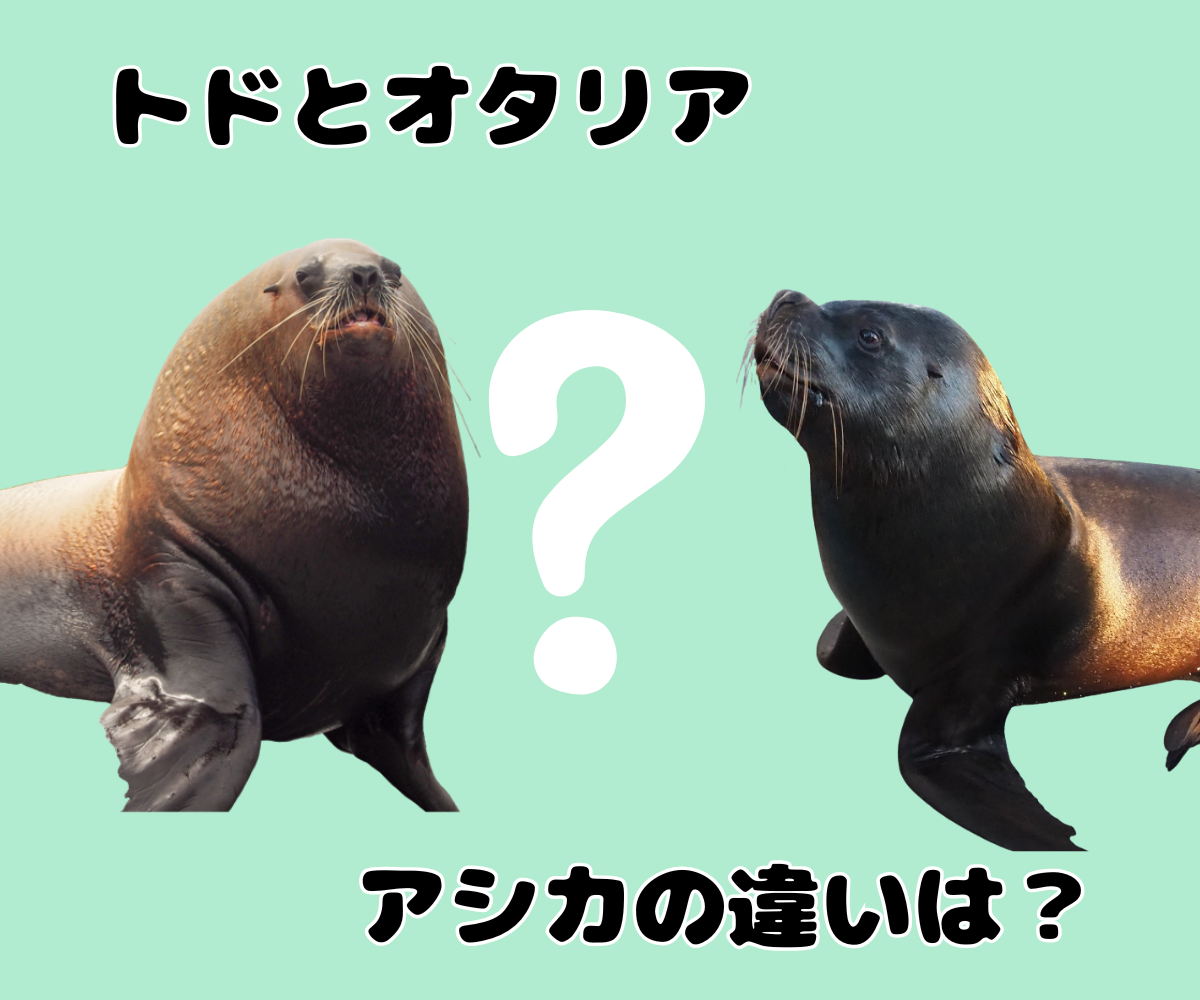
いしかわ動物園~水族館のような水中展示が圧巻!~
ここで会えたひれあし類 今回は石川県能美市にあるいしかわ動物園を紹介します。金沢駅から車で1時間近くかかりますが、ここはわざわざ足を運ぶ価値あり、石川 […]

