タグ:『』の記事一覧
南オーストラリア博物館~ヒョウアザラシと遭遇⁉~
南オーストラリア博物館はアデレード市街地の北部にあり、主要な観光エリアからは歩いていくことができます。南オーストラリア見られる生き物の標本が数多く展示されており、オーストラリアのはく製は本当に海岸で生きたアシカに出会ったような、、、。南極のエリアにはなんとヒョウアザラシが!はく製と頭骨はインパクトがありました。世界的にも貴重な標本で、、、。グッズショップでは靴下も、、、

アデレード動物園~憧れのオーストラリアアシカに会う~
オーストラリアには日本では見れない貴重なひれあし類が暮らしています。 ミナミオーストラリアのアデレードにあるアデレード動物園では、オーストラリアアシカを見ることができました。すらっとした頭に丸い胴体、短いヒレが特徴的で…。展示エリアは自然を再現したような海岸になっていて、ひょうたん型のプールなかをゆったりと…。

室蘭水族館~水中のアザラシに魅せられて~
室蘭水族館ではゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、トドを見ることができました。屋外エリアにある遊園地の奥にあるアザラシプールはキラキラしてて本当に美しかったです。トドプールは本当に渋くて、全面細かい柵で囲まれていたり、トレーナーが指示を出すためのお立ち台があったりします。

男鹿水族館~ヒレアシの水中世界へダイブ~
1分ほどでアシカとアザラシがいる「ひれあし's館」に到着。キラキラと朝日が差し込んで、まるで天国で…その中をアザラシが舞い踊るように泳いでいます。 プログラム以外の時間でも、時折アザラシやアシカが観覧側まで出ているので…

『世界アシカ・アザラシ観察記』を読んで
水口さん自身の活動にフォーカスして、各地のアシカ・アザラシとの出会いや実際に水口さんが感じられたことを紹介した本です。 細やかな言葉遣いから紡ぎだす、自然の風景はまるで私たちまで実際に見たような気持ちにさせてくれます
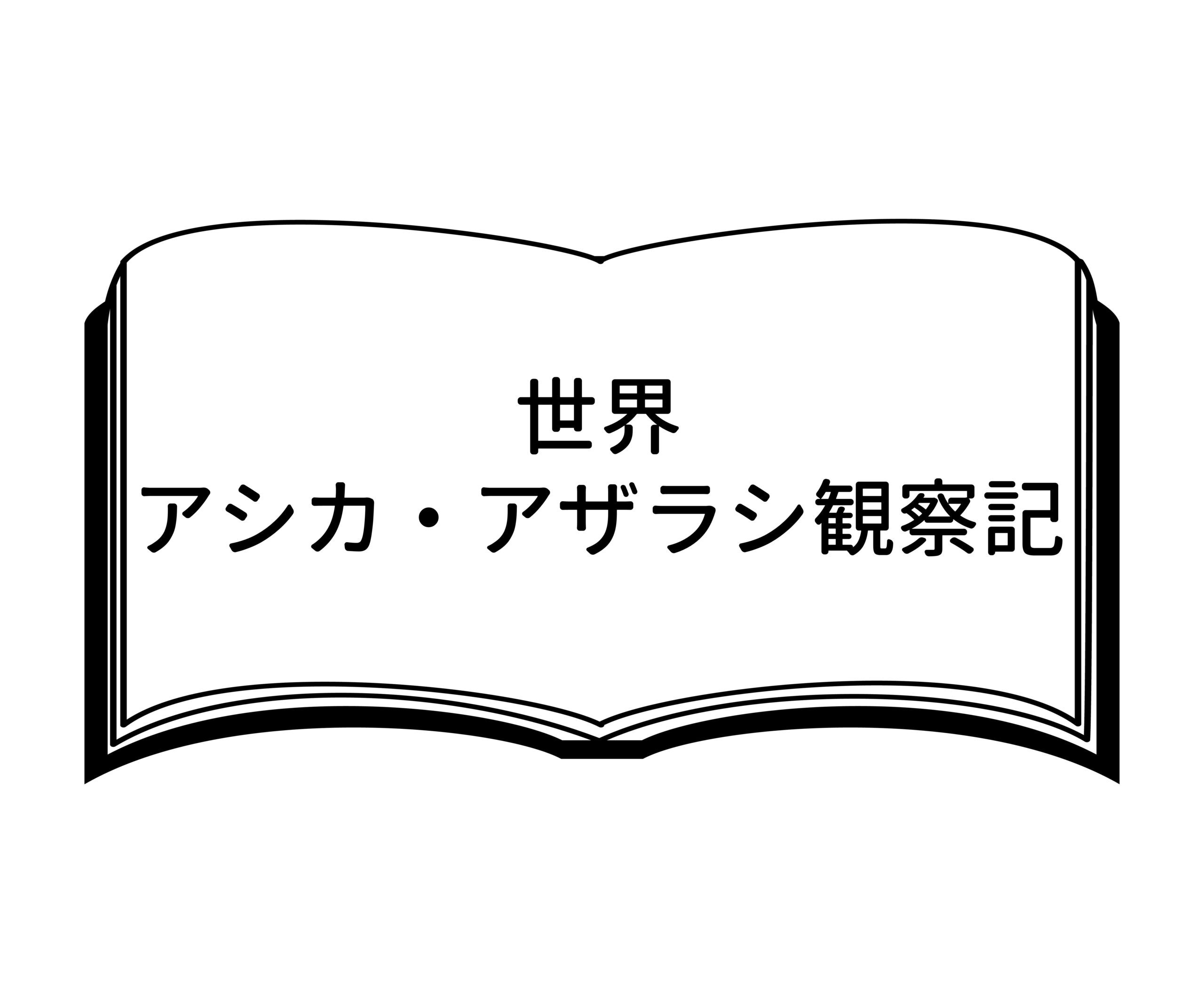
加茂水族館~「なおみ」を偲ぶ~
2022年6月まで飼育されていたキタゾウアザラシの「なおみ」のその後や現在の展示を見るために、8月上旬に加茂水族館を訪問しました。ここではゴマフアザラシとカリフォルニアアシカが飼育展示されています。なおみは2017年に保護されて2022年まで飼育されていました。日本では貴重なアザラシで…。

アクアマリンふくしま
~「くらまる」を偲ぶ~
2023年7月25日に日本で唯一飼育展示されていた、クラカケアザラシの「くらまる」が死亡しました。暑さに弱いので、いつも冬季のみの展示で…涼しいバックヤードで暮らしていました。餌量や薬の量が全く違っていて、飼育の難しさを垣間見ることができました。

【鴨川シーワールド】
~世界でも超貴重なセイウチの全身骨格~
鴨川シーワールドは千葉県・鴨川市にある日本でもトップクラスの規模を誇る水族館です。セイウチの全身骨格標本は世界でも非常に貴重で…陰茎骨やキバが立派でした…。 アシカk科、アザラシ科、セイウチ科を全て見れます。

カリフォルニア州・モントレーに暮らすゼニガタアザラシ
モントレー市自体が西海岸でも特に人気の観光地で、野生のアザラシやアシカに会うこともできます。目の前に生き物が来ることがあります。今回の訪問では野生のゼニガタアザラシとカリフォルニアアシカに会うことができました。

アニョヌエボ州立公園のキタゾウアザラシ その②
道中に突然アザラシに遭遇することもあります。縄張りを持てなかったオスは海岸を離れて砂丘の上まで来ることがあるそうです。海岸ではロープが張られているので安全な距離を保つことができます。海岸線の近くではオスのアザラシが縄張り争いをしています。

